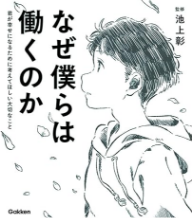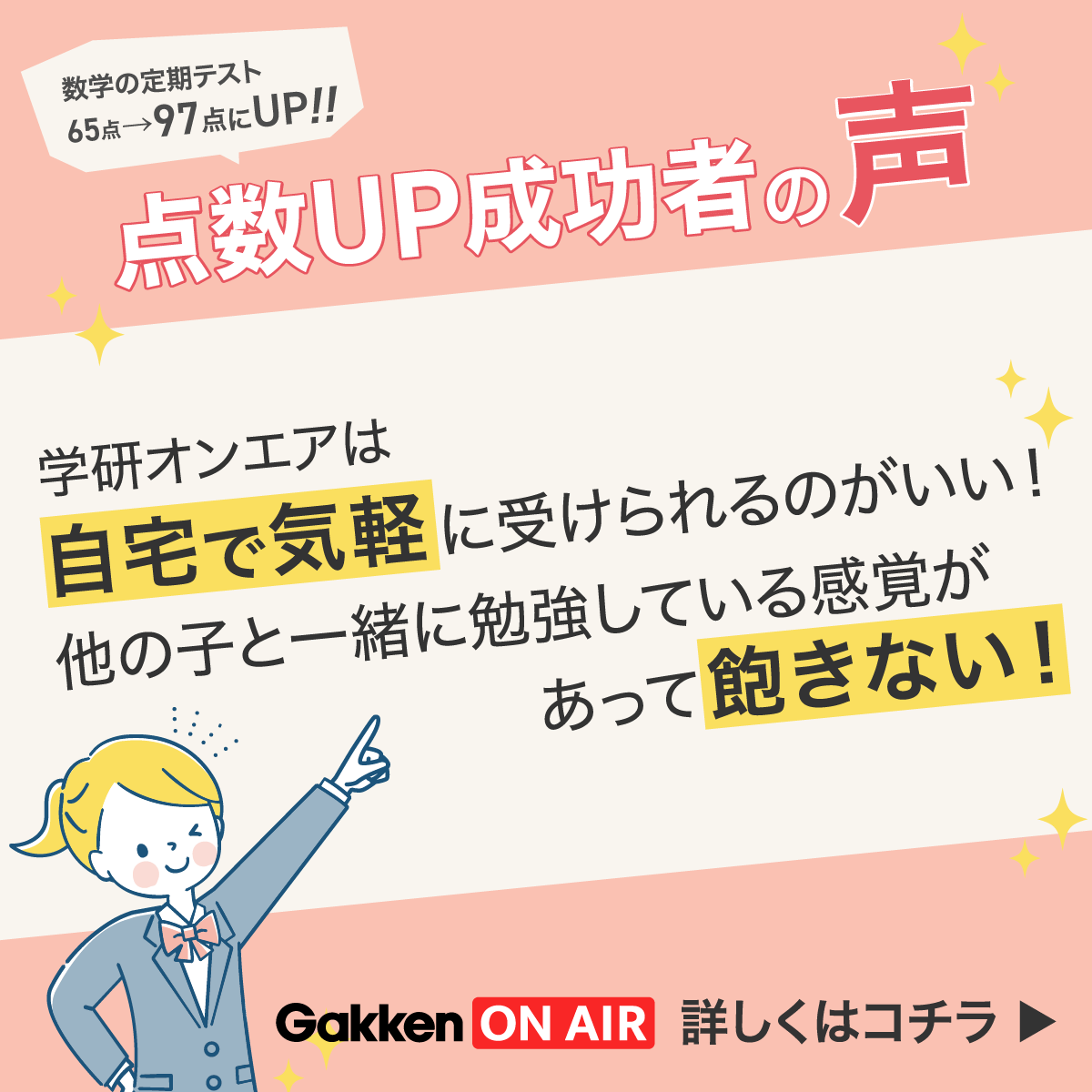中学生になると通知表の成績だけでなく、内申点も気にする必要があります。
「でも、内申点ってどうやって計算するの?」とお悩みの親御さんやお子さんは多いのではないでしょうか。
本記事では内申点の計算例を紹介するとともに、内申点の重要性やアップさせる5つの方法について解説します。
記事の後半では内申点を上げる際におすすめの勉強法も紹介しているので、高校受験対策にお役立てください。
内申点とは

内申点は受験の合否に影響する重要な指標とは分かっていても、実際にはどのように評価されるのか分からない方も少なくありません。
はじめに、内申点がどのような指標なのか解説するとともに、対象科目および評価基準について解説します。
これから受験を控えている方はもちろん、親御さんもぜひご一読ください。
評定のこと
内申点は高校受験の際に提出する調査書に記載される点数で、正式には評定や調査書点、調査書素点などと呼ばれています。
通知表には各学期ごとの成績や出席・欠席日数、早退・遅刻などの情報が記載されており、生徒や保護者が学業の習熟度を知るための目安の1つです。
一方、調査書(内申書)には受験する高校側が参照できるよう、通知表の情報をもとにした受験生としての基本情報が記載されます。
調査書には生徒の成績だけでなく授業への取り組み方や生活態度、部活動における成績、生徒会を通しての活動などの情報も含まれます。
対象科目と評価基準
内申点の対象科目は主要5教科(国語・数学・英語・理科・社会)および実技4教科(保健体育・音楽・美術・技術家庭)です。
各教科ごとに1〜5段階で評価され、合計点が内申点となります。
また、内申点の元となる通知表の成績には、以下の3点も加味されることを覚えておきましょう。
- 知能・技能
- 思考力・判断力・表現力
- 主体的に取り組む態度
上記3つのうち知能・技能に関しては、普段の学習や試験内容が反映されるため、もっともわかりやすい評価基準です。
思考力・判断力・表現力はレポートや作文、ディスカッション、作品の制作・発表などが評価されます。
また、授業や課題に積極的に取り組む姿勢も内申点に反映されます。
内申点の計算法
内申点は主要5教科および実技4教科を1〜5段階で評価して合計点を算出するのが基本です。
ただし、都道府県により内申点の計算方法が異なることを知っておく必要があります。
東京都ほかいくつかの県における内申点の計算例と合わせて解説します。
内申点の計算法は都道府県で異なる
内申点の計算方法は全国共通ではありません。
例えば埼玉県では中1から中3までの成績が内申点に加味されますが、東京都では中3の成績のみが内申書の対象です。
また、主要5教科と実技4教科で計算法が異なるケースもあるため注意が必要です。
内申点に関しては都道府県ごとに独自の計算基準を設けているため、お子さんが受験する高校について調べておきましょう。
内申点の計算例
内申点の計算法は都道府県により異なります。
ここでは例として東京都と千葉県、埼玉県の内申点の計算法を紹介します。
東京都
東京都では中3の成績から内申点を算出します。
主要5教科と実技4教科の合わせて9教科に関して、5段階評価をしたうえで内申点を算出します。
例えば9教科すべて5段階評価で3の場合、内申点は9×3=27です。
ただし、実技4教科に関しては内申点が2倍になるため、実際には27+12で39となります。
千葉県
千葉県では中1から中3の成績をもとに内申書を算出します。
主要5教科と実技4教科の合わせて9教科を5段階評価をしたうえで内申点を算出します。
例えば9教科すべて5段階評価で3の場合、内申点は9×3×3=81です。
ただし、千葉県内の公立高校では内申点に0.5〜2の範囲で「Kの数値」を掛けるのが特徴です。
Kの数値はレベルが高い高校ほど低くなる傾向にあります。
埼玉県
埼玉県では中1から中3の成績をもとに内申書を算出します。
ただし、埼玉県内の高校では学科やコースごとに1・2年時と3年時の比率が異なります。
例えば、学年間の比率が「1:1:2」の高校の場合、9教科すべて5段階評価で3であれば、内申点は9×3×2+9×3×2=108です。
多くの高校で3年時の成績の比重を高くしている点が特徴です。
内申点の重要性
内申点の重要性としては以下5つの点が挙げられます。
- 高校受験の合否を左右する
- 総合的な能力の指標となる
- 自己アピールにつながる
- 受験の際に余裕が生まれる
- 進路選択の幅を左右する
公立高校の多くが入試の成績だけでなく内申点を重視しているため、内申点は高校受験の合否に直結します。
また、内申書(調査書)には学業以外の取り組みも記載されているため、入試に際して自己アピールにもなります。
内申点が高ければ合格に必要な点数が下がるため、受験の際に余裕が生まれることも重要なポイントの1つです。
内申点が高ければ上位の高校にチャレンジできますが、内申点が低いと希望の高校を受験できない可能性があります。
内申点の上げ方5選
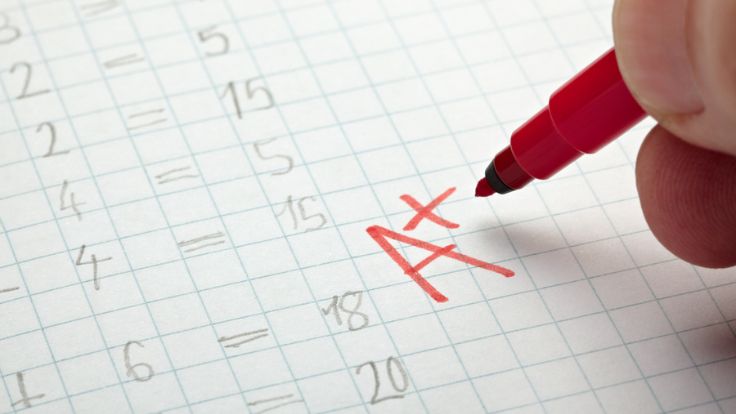
高校受験の際は内申点が重視されるため、普段から以下5つの取り組みで内申点アップを目指しましょう。
- 小テストや定期テストで高得点を取る
- 副教科も手を抜かない
- 提出物のクオリティを高く保つ
- 積極的に授業に参加する
- 検定試験を受ける
それぞれについて詳しく解説します。
内申点の上げ方①小テストや定期テストで高得点を取る
内申点を上げるためには、小テストや定期テストで高得点を取る必要があります。
定期テストはもちろん、小テストも成績を付ける際の主要な要素です。
中学校の成績は絶対評価のため、点数が高ければ高いほど5段階で「5」の評価を得やすくなります。
例えば東京都の場合、5段階でオール4とオール5とでは、内申点が13点(65点満点中)も差が生じます。
内申点の上げ方②副教科も手を抜かない
内申点を上げるためには、副教科も手を抜かないようにしましょう。
英語や数学が苦手でも、体育や家庭科が得意な方は、むしろ内申点を上げる絶好のチャンスです。
特に東京都の場合は実技4教科に関して内申点が2倍になるため、積極的に学習に取り組みましょう。
美術や技術に関しては確実に作品を提出するのがポイントです。
内申点の上げ方③提出物のクオリティを高く保つ
提出物のクオリティを高く保つのも、内申点を上げるポイントの1つです。
技術や美術に関しては、クオリティの高い提出物が成績に直結します。
また、主要5教科に関しても課題やレポートのクオリティを高く保つと、5段階評価および内申点が上がりやすくなります。
仮に技術や美術が苦手であっても、提出物を出さないのは絶対にNGです。
内申点の上げ方④積極的に授業に参加する
内申点を上げるためには、積極的に授業に参加しましょう。
通知表の成績は定期テストや小テストだけでなく、授業や課題に主体的に取り組む態度によっても左右されます。
授業態度が悪いのは論外ですが、積極的に発言や挙手をしないと、内申点を上げるチャンスを逃します。
挙手して答えを間違っただけで成績が下がる可能性は低いため、積極的に授業に参加するのがおすすめです。
内申点の上げ方⑤検定試験を受ける
日本漢字能力検定(漢検)や実用英語技能検定(英検)など、検定試験を受けるのも内申点を上げる方法の1つです。
漢検に関しては3級以上を取得していると、高校受験の際の加点要素となります。
大阪府の公立高校のなかには、英検2級を取得していると試験の点数が80%担保されるなど優遇措置が受けられるケースもあります。
検定試験は自分の現在の学力を知るきっかけにもなるため、積極的に受けるのがおすすめです。
高校受験の内申点を上げるなら学研オンエアがおすすめ!
高校受験の内申点を上げたい方には、学研オンエアがおすすめです。
内申点アップの近道は、学校の定期テストや小テストで高得点を取ることです。
学研オンエアならトップ講師の授業をリアルタイムで受けられるうえ、自分が苦手とする問題をAIが選択して出題してくれます。
また、無料で使える自習室で他の生徒とコミュニケーションが取れるため、学習に対するモチベーションを維持しやすい点がメリットとなっています。
内申点とは?|内申点の重要性や5つの上げ方も紹介!まとめ
内申点は正式名称を評定や調査書点といい、高校受験の合否を左右する重大な指標です。
内申点は通知表の成績をもとに算出されるため、定期テストや小テストで高得点を獲得し、5段階評価の5を目指すのがポイントです。
ただし、通知表の成績には学力以外の要素も加味されるため、普段から授業に積極的に取り組み、検定試験にもチャレンジしましょう。
学校の成績をアップさせたい生徒や親御さんには、トップ講師の授業がオンラインで受けられる学研オンエアがおすすめです。
初月は無料で試せるので、内申点アップにお役立てください。