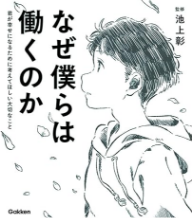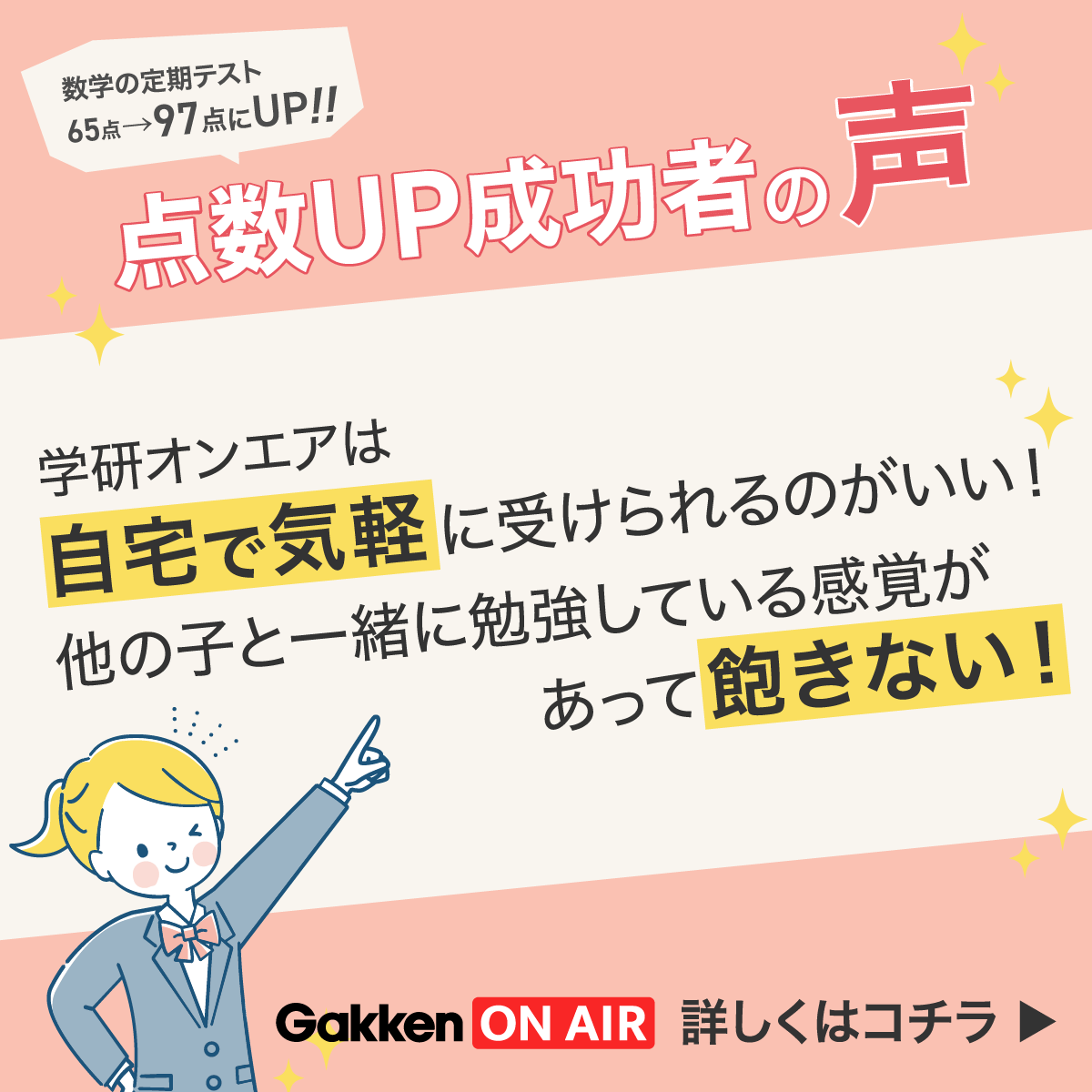自学はその名の通り自分で取り組む学習ですが、小学生の場合は家庭で自学ノートを用いて勉強することを意味するのが一般的です。
小学生の間から自学に取り組むと家庭学習の習慣が身に付き、後々の定期テストや受験の際にもプラスになります。
本記事では自学に取り組む際のポイントや小学生向けの自学ネタを学年別に紹介します。
自学のネタにお困りの方や、子供が家庭学習をしないとお悩みの親御さんは参考にしてください。
自学ってなに?

自学は他人の力を借りずに自分の意志で行う学習を意味しますが、一般的には子供が自分で学びたいことを決めて行う家庭学習を指します。
家庭での自学の際に用いられるノートを「自学ノート」と呼ぶこともあるため、本記事では自学ノートを用いて取り組む勉強のことを自学として話を進めます。
自学ノートの使い方に決まりはありませんが、以下のような目的で用いて学習を進めるのが一般的です。
- 学校で学んだ内容の復習および予習
- 自分の興味がある分野を掘り下げて調べる
- 自分が苦手にしている分野を取り上げて克服する
例えば漢字に関する自覚に取り組む際に、文字の成り立ちを調べる方法もあれば、何度も同じ文字を書いて覚える方法もあります。
自学ノートのメリット・デメリット
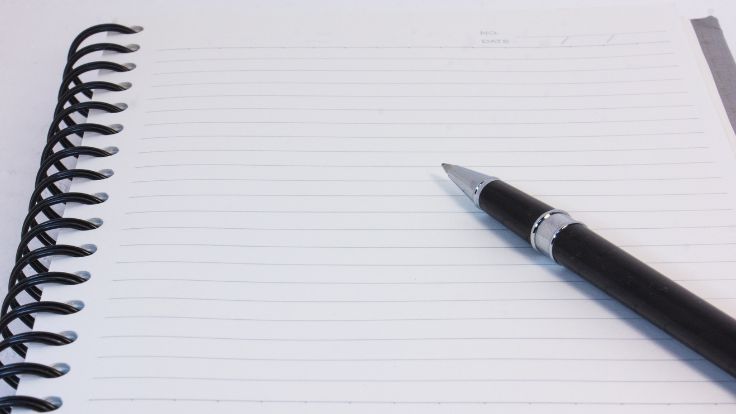
自学ノートのメリット・デメリットとしては以下の点が挙げられます。
メリット
- 自分の興味がある分野に楽しく取り組める
- 家庭学習の習慣が身に付く
- 記憶が定着しやすくなる
デメリット
- 学習内容が偏る恐れがある
- 自己満足で終わる可能性がある
- モチベーションの維持が難しい
それぞれについて解説します。
自学ノートのメリット
自学ノートのメリットとしては学習する内容に制限がなく、自分の興味がある分野に楽しく取り組めることが挙げられます。
興味がある分野を掘り下げることで理解が深まり、記憶に残りやすくなる点もメリットといえるでしょう。
自学ノートを学習内容の振り返りや予習に使えば家庭学習の習慣が身に付くうえ、記憶が定着しやすくなります。
定期テストや入試の際にも強みとなるのは間違いありません。
自学ノートのデメリット
自学ノートのデメリットとしては、学習内容が偏る傾向にある点が挙げられます。
興味のある分野を掘り下げられるのが学習ノートのメリットですが、苦手な分野を避けると学習内容が偏ることは避けられません。
自発的に取り組む学習ノートですが、やっただけで採点や振り返りを怠ると、自己満足で終わる可能性があります。
また、義務的に行う宿題とは異なり、自発的に取り組む自学ノートはモチベーションを維持するのが難しい傾向にあります。
自学に取り組む際のポイント

自学に取り組む際は以下5つのポイントを押さえておく必要があります。
- ゴールを設定する
- 時間を決める
- 完璧を求めすぎない
- 学習環境を整える
- 継続する
自学に取り組む際のポイント①ゴールを設定する
自学ノートでの学習に取り組む際は、ゴール(目的・目標)を設定することが欠かせません。
ゴールを設定しないと達成感が得られず、ただダラダラと作業を続けるだけに留まりがちです。
ポイントは小さなゴールと大きなゴールを設定することです。
小さなゴールとしては小テストや定期テストで良い点数を取る、大きなゴールとしては受験に合格するなどの例が挙げられます。
自学に取り組む際のポイント②時間を決める
自学ノートでの学習に取り組む際は、時間を決めるのもポイントです。
毎日決まった時間に自学を行うと、家庭学習の習慣が身に付きやすくなります。
自学ノートに限らず勉強に取り組む時間は長いほど良いと思われがちですが、集中力が持続する時間には限界があります。
毎日30分取り組んでも構いませんし、塾や習い事がない日に1時間取り組むのも良いでしょう。
自学に取り組む際のポイント③完璧を求めすぎない
自学の際は完璧を求めすぎないようにしましょう。
自学ノートは作って終わりではなく、学ぶことの楽しさを知り、教養を深めるために用いることが大切です。
完璧主義に陥ると楽しかったはずの自学が、やらなければならない「義務」になりがちです。
最初はやらないよりマシ程度でも構わないので、少しずつ楽しんで学習できるよう工夫しましょう。
自学に取り組む際のポイント④学習環境を整える
自学に取り組む際は、学習環境を整えることが重要です。
身の回りにマンガやゲームがあると気が散り、学習に集中できなくなるためです。
スマホは電源を切るだけでなく別の部屋に置いておき、視界に入れないようにしましょう。
また、子供が自学に取り組んでいる時間は、親御さんもテレビやゲームをしないよう協力してください。
自学に取り組む際のポイント⑤継続する
自学に取り組む際は継続することが何よりも重要です。
単発で終わると自己満足にしかならず、学びの楽しさを知ったり教養を深めたりする結果は期待できません。
自学の継続にはモチベーションの維持が欠かせません。
大なり小なり目標を設定して達成できたら、ほめたりご褒美を与えたりするのも良いでしょう。
低学年におすすめの自学のネタ

小学生のうちから自学に取り組むと、家庭学習の習慣が身に付き後々まで役立ちます。
小学生低学年の教科ごとの自学のネタとしては以下の例が挙げられます。
- 国語…しりとり、日記、ことわざなど
- 算数…数字の練習、問題作り、掛け算など
- 生活…都道府県、世界の国旗、地図記号など
低学年におすすめの自学のネタ①国語
小学校低学年のうちは学習に対する興味を持たせることが重要です。
最初は教科書の書き取りや文字の練習から始め、ゲーム感覚でしりとりに取り組み語彙を増やすなど工夫しましょう。
毎日の出来事を日記につけるのもおすすめです。
また、親子で楽しみながらことわざの意味を調べるのも良いでしょう。
低学年におすすめの自学のネタ②算数
小学校低学年の子供は、まず数字を丁寧に書くことから始めてください。
足し算や引き算、掛け算の正解がわかっていても、字が汚いと正解と認められない可能性があるためです。
数字を丁寧に掛けるようになったら、自分で問題を作るのがおすすめです。
与えられた問題を解くだけでなく、自分で問題を作るとテストの際に出題意図を理解しやすくなります。
足し算や引き算が問題なくできるようになれば、掛け算にも取り組みましょう。
低学年におすすめの自学のネタ③生活
生活科の自学では、学校の授業ではまだ習わない分野に取り組むのもおすすめです。
例えば都道府県や県庁所在地、名産品などを調べてノートを作る方法があります。
世界の国旗をクイズ形式で覚えるのも良いでしょう。
小学3年生になると社会の授業に地図記号も登場するため、先取りで学んでおくのもおすすめです。
高学年におすすめの自学のネタ

高学年になれば自学のネタを自分で探せるようになりますが、内容が偏らないよう親御さんも参加するのがおすすめです。
- 国語…四字熟語、漢字検定問題、読書感想文など
- 算数…図形、割り算、計算ドリルなど
- 理科…実験、天体、人体など
- 社会…日本の歴史、偉人、ニュースなど
高学年におすすめの自学のネタ①国語
小学校も高学年になると、受験を視野に入れる家庭も増えてくるでしょう。
四字熟語や漢字検定、読書感想文などは、中学や高校の入試の際にも役立ちます。
漢検(実用漢字能力検定)に合格すると、高校入試の際の内申点アップにもつながります。
読書感想文が苦手な子供は多いですが、表現力・読解力・文章力など国語力を上げるのに有益な方法のため積極的に取り組みましょう。
高学年におすすめの自学のネタ②算数
小学校の高学年になると、中学校の数学の基礎となる内容を学び始めます。
中学校に入ってからつまづかないよう、図形の面積の計算法や割り算など、しっかりと覚えるようにしておきましょう。
ケアレスミスを避けるため、計算ドリルに取り組むのもおすすめです。
ただし、あくまでも興味を持って学習に臨めるよう、義務感ではなく楽しみながら取り組むのがポイントです。
高学年におすすめの自学のネタ③理科
理科は実験を取り入れると楽しみながら自学を続けやすくなります。
磁石を用いた実験や観察日記などは、家庭でも続けやすい自学の1つです。
地球をはじめとする太陽系の惑星や星座なども、楽しみながら取り組みやすい自学のネタといえるでしょう。
食事で摂取したものが体内でどのように生かされるのか調べるものおすすめです。
高学年におすすめの自学のネタ④社会
社会のおすすめの自学ネタとしては、日本の歴史が挙げられます。
なかでも戦国時代はマンガやゲームでも取り上げられる機会が多いため、興味を持って学習を進めやすい分野の1つです。
読書が好きな子供は世界の偉人について掘り下げて調べるもの良いでしょう。
また、日々のニュースや感想を自学ノートに記入し、自分なりの考察をするのもおすすめです。
自学のネタに困ったら学研オンエアがおすすめ!
自学のネタに困りがちなお子さんには、学研オンエアがおすすめです。
学研オンエアは13万もの問題から、一人ひとりに適した出題をする点が特徴です。
無料で利用できるオンライン自習室もあり、仲間とコミュニケーションを取りながら楽しく学習が続けられます。
【小学生向け】自学のネタを紹介|まとめ
小学生のうちから自学に取り組むと、家庭学習の習慣が身に付き、来る受験に向けて大きな強みとなります。
自学を続けるためにはモチベーションの維持が必要なため、興味を持って取り組めるネタを探すのがポイントです。
自学のネタにお困りのお子さんや親御は、学研オンエアを試してみてはいかがでしょうか。
AIが多彩な問題を出題するため、飽きずに家庭学習に取り組むことが可能です。