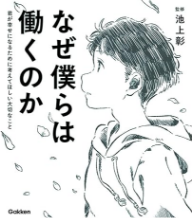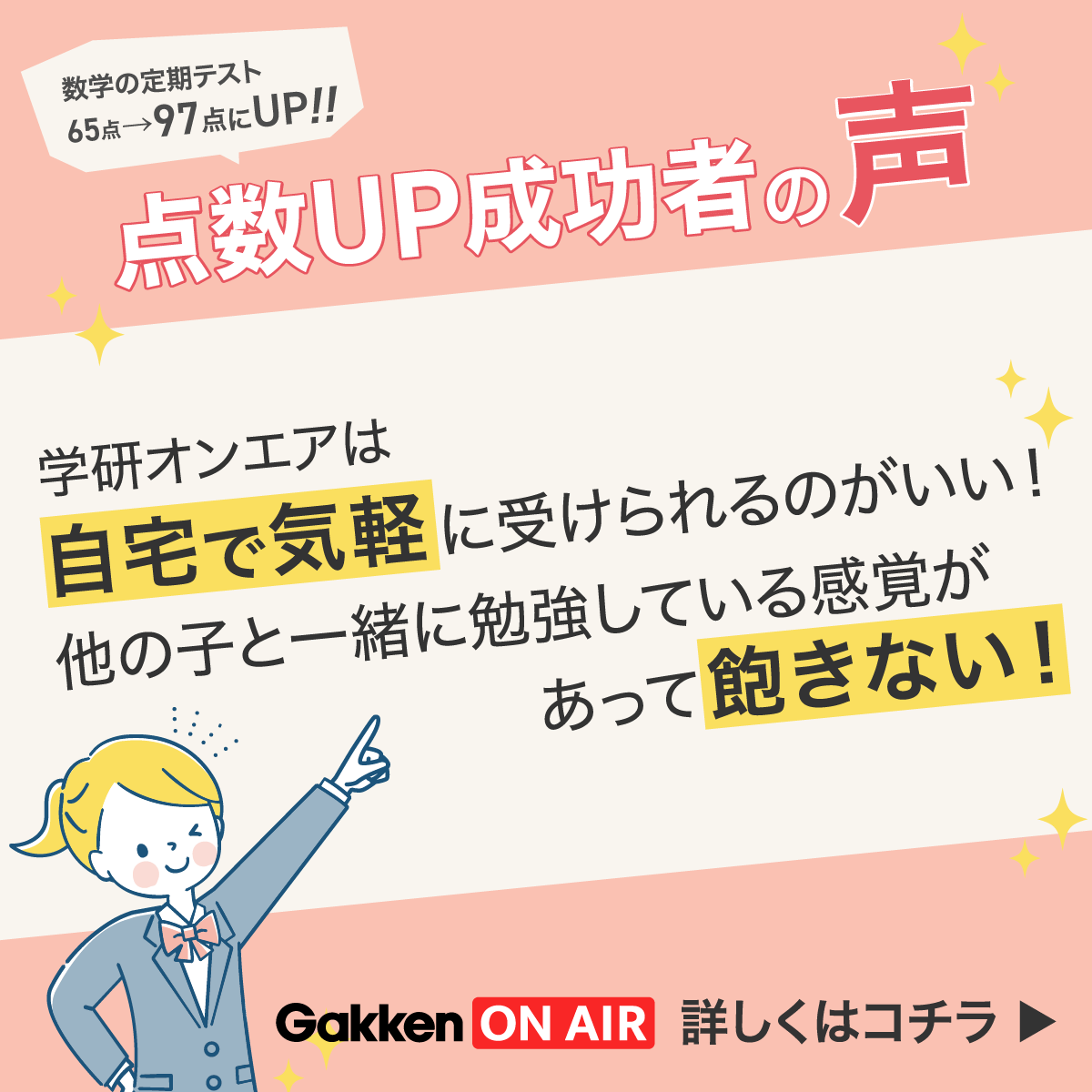中学生になると授業で学ぶ教科が増えるため、小学生と同じような時間配分では学習効率が上がらない可能性があります。
受験勉強はもちろん、中間・期末テストの際も順番を考えて勉強に取り組むと、学力アップや合格率アップにつながるでしょう。
本記事ではどの順番で5教科を勉強するのが効率的か解説するとともに、受験に向けた優先順位の付け方を紹介します。
5教科を勉強する際に順番が重要な理由

5教科の勉強する際に順番が重要な理由は以下のとおりです。
- 順番を考えずに勉強を進めると効率が悪い
- 中間・期末テストに間に合わない
- 入試の前に慌てる羽目に陥る
5教科のなかには覚えるまでに時間がかかるが、いったん覚えてしまえば長く記憶に留まる教科があります。
一方、すぐに覚えられるが、忘れるまでの時間が短い教科もあります。
そのため、順番を考えて試験の際に実力を最大限に発揮できるよう工夫する必要があるのです。
順番を考えずダラダラと詰め込むだけの勉強を続けると効率が悪く、中間・期末テストに間に合わない可能性があります。
また、長期的に学習計画を立てないと、受験の前に慌てて詰め込み型の勉強をやる羽目に陥る危険性もあります。
5教科を勉強する際に効果的な順番
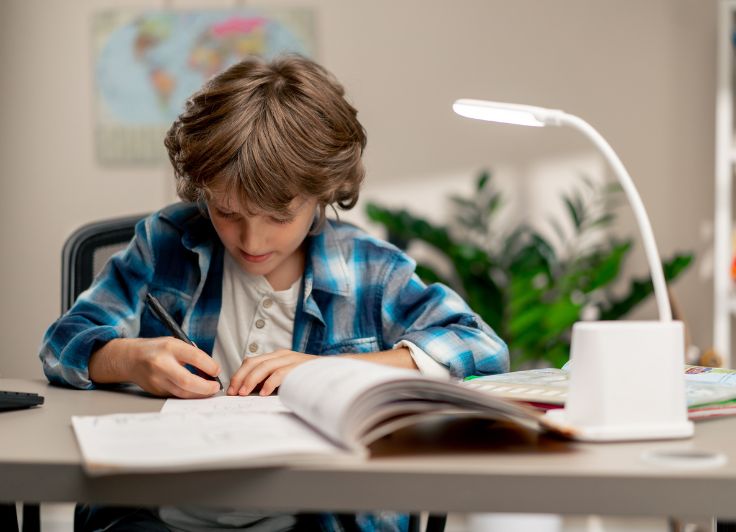
5教科を勉強する際は、以下の順番で取り組むのが効果的です。
- 数学は早い段階で
- 時間がかかる教科も優先的に
- 暗記科目は短期集中で
それぞれについて解説します。
5教科を勉強する際に効果的な順番①数学は早い段階で
5教科を勉強する際は、やり方を覚える教科に早い段階で取り組むのが鉄則です。
やり方を覚える教科の筆頭が、公式などを用いて問題を解く数学です。
公式はいったん覚えてしまえば忘れにくいため、定期テストや入試のかなり前に勉強しても問題ありません。
むしろ早めに公式をインプットしておけば、その後の勉強を効率的に進められるメリットがあります。
5教科を勉強する際に効果的な順番②時間がかかる教科も優先的に
5教科を勉強する場合、時間がかかる教科も優先的に進める必要があります。
時間がかかる教科を後回しにすると定期テストや入試前に慌てるだけでなく、覚えやすい教科に割く時間も削られるためです。
時間がかかる教科の代表が英語です。
英語は文法や単語、長文読解などさまざまな分野の知識・能力が必要なため、早い段階から計画的に取り組む必要があります。
受験に際してどのコースを選ぶにしても、就職を有利に進めるためにも英語力は必須です。
脳が柔軟な若いうちに英語に取り組むと、入試や就職までにライバルに差をつけやすくなります。
5教科を勉強する際に効果的な順番③暗記科目は短期集中で
暗記科目は比較的短期間で習得できるため、短期集中で取り組むのがおすすめです。
歴史の年号や英単語など、単語カードを利用して繰り返し学習するとよいでしょう。
ただし、短期集中=試験直前ではありません。
すぐに覚えられる年号や単語は忘れやすいため、毎日の通学電車のなかやスキマ時間を利用して、何度も取り組むのが大切です。
受験に向けた優先順位の付け方
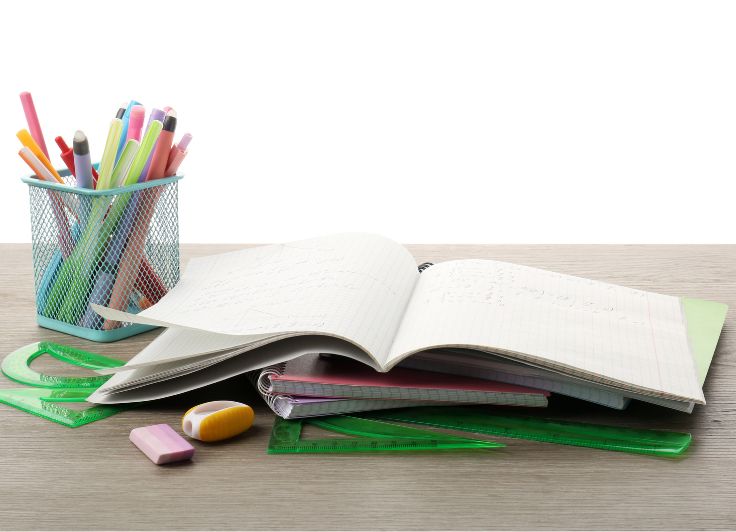
日常的な5教科の勉強の順番だけでなく、受験に向けて以下の優先順位を意識した対策を講じる必要があります。
- 宿題や提出物は最優先
- 計画的に定期テスト対策
- 最後に受験対策
内申点をアップさせ、志望校に合格したい方は参考にしてください。
受験に向けた優先順位の付け方①宿題や提出物は最優先
受験に向けた学習において、優先的に取り組むべきは宿題や提出物です。
宿題や提出物を怠ると内申点が下がり、希望する学校を受験できなくなる可能性があります。
定期テストでよい点数を取っても5段階評価が上がらない場合、宿題や提出物を怠っている可能性が疑われます。
東京都では中学3年生の評価が内申に反映されますが、学習習慣を急に変えるのは難しいため、1年のうちから宿題や提出物に取り組むよう意識しましょう。
受験に向けた優先順位の付け方②計画的に定期テスト対策
日々の学習において宿題や提出物は最優先ですが、定期テスト対策も並行する必要があります。
宿題や提出物はもちろん、定期テストの点数も内申に反映されるためです。
神奈川県では中1・中2の定期テストの結果が内申に反映される一方、千葉県では3年間のテスト結果が評価されるなど、都道府県により基準が異なります。
東京都では中3のテスト結果のみが評価されますが、3年生になって急に頑張っても成績アップは難しいため、1年生のうちから安定して結果を残しておくことが重要です。
受験に向けた優先順位の付け方③最後に受験対策
日々の宿題や提出物に取り組み、定期テストで安定した成績を出せるようになったら、最後に受験対策を行いましょう。
受験対策も志望校合格のために欠かせませんが、受験までの時間を逆算してコツコツ取り組めば間に合います。 また、日々の学習の延長線上に受験が控えています。
定期テストで安定して良い成績を収められるようになれば、内申点がアップして志望校合格が近づくでしょう。
5教科を勉強する際に副教科の順番は?

5教科を勉強する際に、副教科は後回しで構いません。
副教科は受験の際に必要なく、一夜漬けでも対応できる範囲のケースが多いためです。
ただし、後回しにして良いからといって、おろそかにして良い訳ではありません。
たとえば東京都の内申点では、副教科の評定を2倍にして計算します。
内申点をアップさせるためにも、5教科を優先的に勉強したら、短期集中で副教科に取り組みましょう。
高校受験に向けた5教科の勉強法
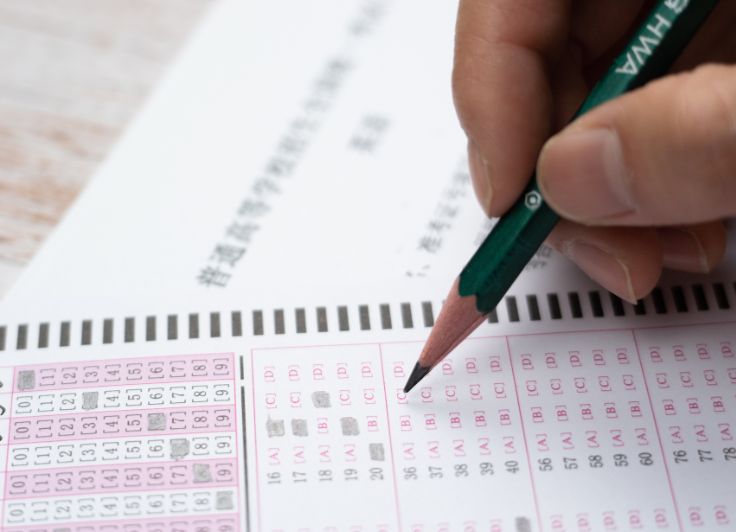
定期テストに比べると、高校受験までにはある程度の期間があります。
日常の学習と同様、高校受験対策に関しても順番を意識すると、効率よく学習が進められます。
ここでは主要5教科に関して、高校受験に向けた勉強法を解説します。
高校受験に向けた5教科の勉強法①数学
数学は解き方を覚えるのが重要な教科のため、早い段階で公式を覚えるなどの対策を講じるのがポイントです。
基本問題を何度も繰り返し、どの公式を用いればよいのか適切に判断できるようになれば、応用問題に取り組みましょう。
数学は多くの問題に取り組めば取り組むほど、成績が向上しやすくなります。
計算ミスをなくすためにも、間違いやすい問題には何度でも取り組み、ケアレスミスをなくしましょう。
高校受験に向けた5教科の勉強法②英語
英語の学習に関しては英単語の習得と文法の理解がカギとなります。
長文を読解したりリスニングに取り組んだりする際にも、英単語の習得や文法の理解は欠かせないためです。
日々の学習で音読に取り組み、単語カードを活用して英単語、および文法に関する理解を深めましょう。
英単語の習得と文法の理解が進んだら、長文読解に取り組み多くの問題に触れるのが重要です。
リスニングに関してはディズニーの映画を字幕なしで見るなど、耳で英語を理解できるよう工夫すると良いでしょう。
高校受験に向けた5教科の勉強法③国語
国語力は数学をはじめ、どの教科に取り組む際にも求められます。
出題者の意図がどこにあるのかを汲み取り正解を導き出せるよう、文法の理解に努め多くの演習問題に取り組みましょう。
古文に関しては源氏物語などを取り上げたマンガで学習する方法もあります。
マンガで大筋を理解しておけば、試験の解答も導きだしやすくなるでしょう。
漢字は見て覚えるだけでなく、実際に何度も書いて習得するのが近道です。
高校受験に向けた5教科の勉強法④理科
理科は生物・化学・地学・物理の4つに大別されますが、個人により得手不得手が出やすい教科の1つです。
そのため、自分の苦手分野の克服に努めるのがポイントです。
得意分野をさらに勉強するより、苦手分野を克服する方が得点アップにつながります。
第一志望の学校にこだわらず、自分が理解できるレベルの問題集から始め、徐々にステップアップしましょう。
高校受験に向けた5教科の勉強法⑤社会
社会は暗記が中心の教科のため、単語カードなどを利用して効率的に記憶を定着させましょう。
歴史に関してははじめに時代の流れを大まかに把握し、登場人物や事件に関して時系列で記憶するのがポイントです。
地理に関しては暗記だけでなくグラフや図表を用いた問題も出題されるため、多くの演習問題に取り組みましょう。
日頃から新聞記事やニュースに目を通し、時事問題について学習しておくのもおすすめです。
5教科はどの順番で勉強するのが効果的?受験に向けた優先順位の付け方|まとめ
5教科は英語・数学・国語にウエイトを置き、空いた時間で理科・社会の学習に取り組むのがおすすめです。
内申アップのため宿題や提出物には欠かさずに取り組み、定期テストで安定してよい点を取るのがポイントです。
受験勉強も大事ですが、まずは基礎的な学力を高めるのが先決です。
志望校合格には日々の学習への取り組みが深く関わっていると理解し、受験日までの日数を逆算して効率的に学習を進めましょう。