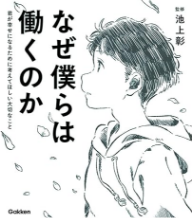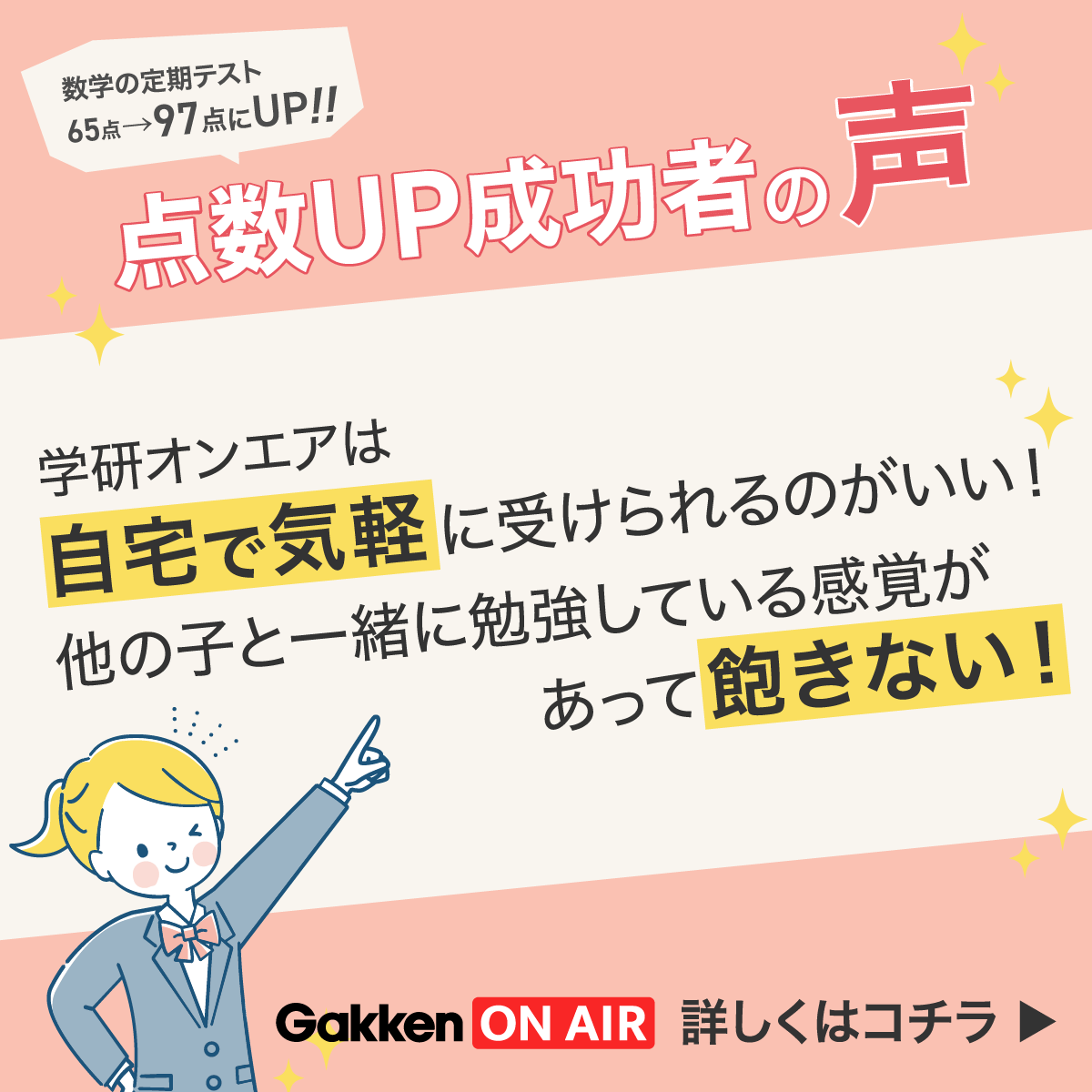「小学生の子供に、どのようにお小遣いを渡すべきだろう・・・」と感じる保護者の方へ。
今回の記事では、調査データから分かる保護者の見解や小学生のお小遣い事情、効果的な金融教育を育む渡し方についてご紹介します。
「ウチの子にはまだお小遣いをあげていないけど、ほかのお子さんはどのくらいもらっているんだろう・・・」
「学ぶことを意識してお小遣いを渡したいけど、どう支払うべきか分からない・・・」 とお悩みの方にも、お子さんの今後を見据えたお小遣いプランの選び方をご提案します。
小学生にお小遣いは有り?無し?

まず、お子さんにお小遣いを渡す保護者の皆さんの意見をまとめました(出典1)。
小学生のお小遣い制度について、一般的にどのように考えられているのでしょうか?
保護者ご自身のお考えやお子さんの性格に照らし合わせて、参考にしていただくのも良いかもしれません。
【有り】派の意見
お金を稼ぐ大変さを学んでほしい
自発的に行動する姿勢を評価したいから
家事労働のモチベーションを上げるためにピッタリだから
労働の意義や金銭管理の大切さを学んでほしいから
善意によるお手伝いや必要な家事以外なら、対価を渡すべきと考えているから
お金を貯めるプロセスを実感してほしいから。
有り派の意見として、「社会勉強の一環として」や「お手伝いのモチベーションを上げたい」、「自力で得たお金で購入した物を、大切に扱えるようになってほしい」という見解が多くありました。
【無し】派の意見
家族の一員としてお手伝いは当たり前に取り組むことだから
お小遣いが無いとお手伝いをしなくなるから
お小遣いを渡すと、感謝の気持ちが薄れてしまうから
一方無し派の意見として、「お手伝いの目的や意味を大切にしてほしい」と考える層が多く見受けられます。
特に、お手伝いの報酬として渡されるお小遣いについて、**「将来家庭をもったときに、自発的に家事をしなくなってしまう」**と不安視する声が多いようです。
出典1:お手伝いにお小遣いは必要?導入する際のルールや金額は【保護者のホンネ】|ベネッセ教育情報サイト
https://benesse.jp/kosodate/202311/20231120-1.html
小学生の平均金額&使い道は?

2023年9月に実施された調査から、小学生のお小遣い事情について以下の結果が判明しました(出典2)。
【低学年(1~2年)】の平均
・平均:966円 中央値:800円
小学校低学年の段階だと、本人によるお金の管理が難しいため、お金の使い道を保護者が一緒に共有しておくことが望ましいでしょう。
特に、ゲームやマンガなどの娯楽系の出費は、保護者がしっかりと管理することが大切です。
【中学年(3~4年)】の平均
・平均:1,121円 中央値:1,000円
低学年よりも計算スキルが身についているためか、自分でお金の計算ができるお子さんが増えるのでしょう。
低学年よりも高めにお小遣いを設定しているご家庭も多いことが分かります。
興味関心の幅が広がる分、低学年と比較すると使い道も多様になっていく年頃です。
お子さんの気持ちを尊重しつつ、必要に応じてお小遣いを渡すと良いでしょう。
また、「勉強に必要なノートや消しゴム、シャープペンシルなどの費用は、お小遣いとは別に支給する」などのルールを設けることも検討してみてください。
【高学年(5~6年)】の平均
・平均:1,653円 中央値:1,000円
中学年よりも交友関係や活動範囲が広まっていくお子さんが多い傾向にあるようです。
管理能力も問題ないと捉える保護者も多いためか、お小遣いの金額も更に高く設定されています。
友人との食事や誕生日プレゼントなどの交遊費や、お出かけする際の交通費の占める割合も多くなる年頃です。
保護者の目が届かない範囲で行動する機会も増えるため、周りに合わせて無理なお金の使い方をしていないか、定期的にチェックしていくことが望ましいでしょう。
小学生の主なお小遣いの使い道
金融広報中央委員会の調査データによると、最も多い使い道は「お菓子やジュース」と判明しています。
いずれの学年でも1位となっていますが、年齢層が上がるにつれて使い道の種類が増え、高いものを購入する傾向にあるようです(出典3)。
出典2:ママソレ|【2023年最新】お小遣いの平均はいくら?小学生・中学生・高校生別のパパママにアンケート
https://mama.chintaistyle.jp/article/survey-2023-okodukai-heikin/
出典3:子どものくらしとお金に関する調査(第3回)2015年
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/kodomo_chosa/2015/
目的ごとに選ぶ!お小遣いの渡し方

お小遣いの渡し方には「定額パターン」「報酬パターン」「都度払いパターン」「一括パターン」の4種類があります。
金融教育を意識しつつ「お子さんに最も学んでほしいことは何か」を明確にすることが非常に重要です。 それぞれの特徴をふまえて、ご家庭に合ったやり方を実践してみてください。
定額パターン
一定の金額を定期的に渡すパターンです。
【メリット】
次回のお小遣い日までの期間を考えながらお金を使う必要があるため、計画的に管理する習慣をつけやすい方法です。
小学生のお子さんが、「計画性」や「金銭管理スキル」を磨くうえでも取り組みやすい、定番のパターンといえるでしょう。
【デメリット】
ただし、無条件で一定額手に入る方法のため、**「お小遣いをもらえて当たり前」**と捉えてしまう場合もあります。
この場合、お手伝いや学業成績でボーナスをプラスする報酬パターンを組み合わせることで、対価として金銭を得られることを実感しやすくなるでしょう。
報酬パターン
家事のお手伝いや学校の成績など、労働や成果の報酬としてお小遣いを渡すパターンです。
【メリット】
「労働や成果の対価として収入が手に入る」という感覚が養われやすくなるため、お子さんのモチベーションを高めるきっかけになるでしょう。
特に、お子さんに対して「お金のありがたみ」を学んでほしいと考える方にオススメのパターンです。
【デメリット】
この方式を選ぶことで、お小遣いという報酬を前提にしない物事に対して、意欲的に取り組まなくなる可能性があります。
報酬パターンを取り入れる場合、報酬を渡す基準やルール決めに注意が必要です。お子さんと保護者の方でしっかりと話し合い、お互いに納得できるラインを共有しておくことが重要です。
都度払いパターン
お子さんが保護者に対して必要なものを伝えて、お小遣いをもらうパターンです。
【メリット】
「なぜ必要なのか」を分かりやすく説明し、相手に納得してもらうためのプレゼン力を向上させることができます。
妥当な理由や根拠を用意し、簡潔にアピールする能力を鍛えていくことは、お子さんの今後を考えても身になる経験と言えるでしょう。
保護者視点からでもお子さんのお金の使い道を把握しやすく、必要な分だけ渡す方式のため無駄遣いを減らしやすいメリットもあります。
【デメリット】
プレゼンが成功すればその都度お金を手に入れることができるので、金銭管理のスキルが身につかない可能性があります。
そのため、お子さんにお金を渡した後「プレゼンされた通りの物を購入しているか」を必ずチェックしておくと安心です。
お子さんとレシートの回収を約束するなど、使い道のチェックを徹底すると良いでしょう。
一括パターン
年に1度、決まったタイミングで1年分のお小遣いをまとめて渡すパターンです。
【メリット】
定額パターンよりも長い期間にわたって、お小遣いをやり繰りするスキルを育むことができます。
年に1度のみお小遣いが支給されるパターンのため、長期的な目線で金銭を管理できる思慮深い姿勢を培えるでしょう。
【デメリット】
しかし、管理能力が未熟なお子さんの場合、後先考えずにまとまったお金を無駄遣いしてしまう恐れがあります。
使う予定の無いお金の貯め方や使い切ってしまった場合の対処法など、親子で必ず共有しておくと安心でしょう。
お小遣いを渡す際のポイント
小学生にお小遣いを渡す際、以下の4点を意識することも大切です。
お小遣いの元は「保護者が働いて得たお金」であること
いずれのパターンでも、あらかじめ上限を定めておくこと
お小遣い帳(紙・アプリなど形態不問)をつけること
少額でも仲良しのお友達でも、金銭のやりとりは行わないこと
お子さんの理解力や行動範囲に合わせて伝え方を工夫することで、個々の成長に合わせた金融教育を目指せるでしょう。
「何を学んでほしいか」を軸に、実りあるお小遣いライフを!|まとめ
小学生のお小遣い事情や、渡し方のポイントについて解説していきました。
お小遣いを通じて、管理能力や金銭感覚を養うだけでなく、お金のありがたみや対価として手に入れる大変さなど、将来的にも役立つ学びを得ることができます。
お子さんご本人やご家庭の方針をふまえたうえで、ぜひお小遣い制度にチャレンジしてみてくださいね。