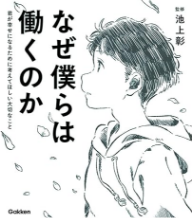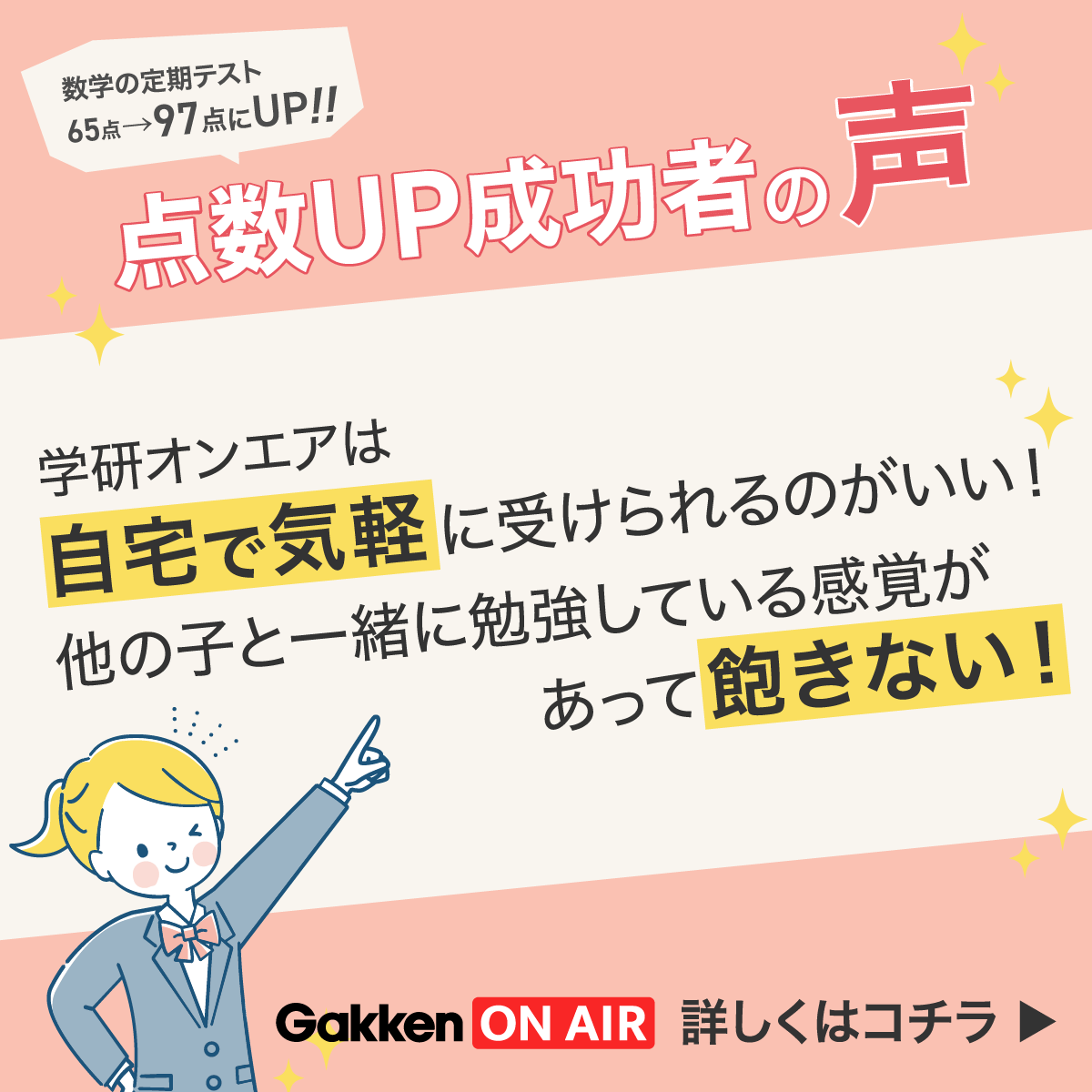「受験勉強はいつから始めるのがベストなの?」 という疑問は、多くの方が一度は考えた経験があるかもしれません。
高校受験でも大学受験でも、志望校の受験日から逆算して受験計画を実行していく必要があります。
本記事では高校受験、大学受験のそれぞれの要点をまとめ、それぞれに効果的な対策をご紹介いたします。
中学生の受験勉強はいつから始めるべきか

結論として、受験生の中学3年生はもちろん、中学1年生・2年生の段階からでも高校受験を意識することで、より有意義に受験勉強を進められるでしょう。
「高校受験の対策って、いつから始めればいいの?」とお悩みの学生さんや保護者の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
受験勉強は中学3年夏から始めるお子さんが多数
一般的に、【中学3年の夏頃から】高校受験の勉強を始めるという方が多いようです。
中学3年生の夏を境に部活動の引退シーズンが始まることから、それ以降は受験モードに切り替えていく方が多いと言えるでしょう。
しかし、部活動に専念してからいきなり受験勉強を始めるのは、身が入りづらいという意見もあるはず。
本人の学習状況や志望校、得意・不得意科目によって最適なタイミングは異なりますが、遅くとも中学3年の夏頃までを目安に考えるとよいでしょう。
中学生の受験は【入試成績】&【内申点】がポイント
高校受験の入試では、中学1・2年生の学習範囲が多く出題される傾向が強いため、中学1年生の段階から基礎学力を高めていくことが望ましいです。
受験直前になってから後悔しないように、苦手科目やつまずきを解消できておくと、より安心でしょう。
また、通知表の内容を数値化した【内申点】も、中学生の受験勉強に少なからず影響を与える要素です。
公立高校の一般入試であれば、【入学試験の成績】+【内申点】を合算した点数で選抜が行われるため、中学3年間分の定期テストの点数や授業態度、課題の提出状況なども合否につながる可能性があります。
私立高校の一般入試では、おおむね入学試験の点数で合否が決まる傾向があるようですが、推薦入試では内申点も評価基準となるので、成績を上げておくに越したことはないでしょう。
内申点は定期テストなどの勉強の成果はもちろん、普段の生活態度も評価対象になりますので、今からでもすぐに取り組める受験対策の一環と言えるでしょう。
公立高校の受験対策
公立高校の受験シーズンは、推薦入試が2月上旬、一般入試が2月下旬〜3月上旬ごろと言われています。
公立高校を第一志望とする中学生で、私立高校の併願受験を考えている方は、私立高校の試験後に公立高校の試験を受けることになります。
そのため、受験予定の学校の試験日を事前に把握しつつ、それに沿った綿密な学習スケジュールと体調管理を徹底しておくことがオススメです。
私立高校の受験対策
私立高校の受験シーズンは、推薦入試が1月上旬~2月上旬、一般入試が1月下旬~2月中旬ごろと言われています。
そのため、志望校や入試形態によっては、最短で年明け早々に入試日を迎える可能性があるため注意が必要です。
滑り止めとして受ける「併願受験」や、第一志望の「専願」など、私立高校にはさまざまな入試パターンがありますので、志望順位をふまえて適切な方法を選びましょう。
中学生向け|学年ごとにオススメの受験勉強

中学生が高校受験するうえでオススメする勉強スタイルを、学年ごとにまとめました。
いつから何を始めるべきか検討する際、お子さんの学年と照らし合わせて参考にしてみてください。
中学1年|受験勉強を意識した基礎力を育む
中学1年生の学習範囲はとても重要です。
なぜなら、中学最初の1年間で習う基礎は中学2・3年の学習範囲のベースになるためです。
中学1年の時点でつまづきを放置してしまうと、受験期になってから学習しても分からないことが多く、勉強がスムーズに進まない可能性があります。
分からない問題に直面した際に、「分からない問題をそのままにしない」という意識を持たせ、理解できるまで向き合う姿勢を育むことが理想的と言えるでしょう。
中学3年間の土台とも呼べる1年間となりますので、生活態度と合わせて、今後の受験勉強の質にも繋がります。
中学2年|長期休暇を活かして集中学習&3年前までに対策スタート
部活動や委員会なども盛んになり、場合によっては部長などの役職に就くこともある中学2年生。
忙しくなりがちな中学2年生は、空き時間の有効活用が受験勉強のポイントとなってきます。
夏休みなどの長期休暇を活かして、それまで習った範囲の復習+苦手な問題の克服に集中できるのが望ましいでしょう。
数学や英語は進学するにつれて苦手の影響が出やすい科目のため、早いうちに対策ができれば、受験勉強をもっと有利に進められます。
また、中学3年生になる少し前の1〜3月に、2年間の学習内容をおさらいすることをオススメします。
このタイミングで一旦内容をまとめることで、受験勉強だけでなく3年生の学習範囲にもアドバンテージを取ることができるからです。
中学3年|最後の総復習&直前まで予行演習
ほぼ全ての地域で、中学3年生の成績が内申点として志望先の高校に送られます。
そのため、1学期の定期テストから確実に点数をとりつつ、普段の生活態度にも気を配ることで、志望合格へ近づくことができるでしょう。
【~中学3年生の夏休み前まで】
中学3年生の1学期は、これまで同様に授業や提出物、定期テストにしっかりと取り組みながら、中学2年生までの苦手分野を中心に復習に取り組みましょう。
これまで学んだ範囲の基礎問題に取り組み、抜け漏れがないかチェックしておきましょう。
定期テストで間違った問題を解き直すだけでも、苦手な範囲や傾向を把握するのに役立ちます。
1・2年生の学習内容に穴があると、3年生の学習内容が難しく感じることもありますので、この場合は、1・2年生の学習内容を復習しても良いでしょう。
しかし、学習時間が確保できない場合は無理をせず、3年生の学習を優先してから低学年の復習に臨むのがオススメです。
また、6月頃からは高校の見学会・説明会の時期に差し掛かりますので、志望校を絞り込み積極的に参加しておくと良いでしょう。
志望校の雰囲気や強みを知ることで、受験のモチベーションを高めることにも役立つでしょう。
【中学3年生の夏休み期間】
中学3年生の夏休みは、中学1・2年生&3年生1学期の基礎固めにあてたい期間です。
これまでの学習範囲の、基礎知識の定着&苦手克服に力を入れましょう。
暗記学習の1周目もこの頃までに済ませておくと、2学期以降の負担を減らせます。
基礎知識の定着&苦手克服が終わり次第、志望校の過去問題集(過去問)に取り掛かり始めましょう。
回数をこなすほど志望校の入試傾向を体感しやすくなり、より効率的に対策ができるようになります。
【中学3年生の9月~冬休みまで】
中学3年生の2学期は、授業や定期テストの勉強を続けつつ、入試に向けた問題演習を始めましょう。
これまでの範囲で苦手なところは基礎固めを徹底し、バッチリな範囲は入試対策の問題演習にチャレンジするやり方が理想的です。
模擬試験が盛んになる時期でもありますので、入試のテスト形式や時間配分に慣れる練習として、積極的に参加しておきたいイベントですね。
学校の定期テストと同様に模擬試験の結果も必ず見直し、間違った問題の解き直しも忘れずに取り組みましょう。
模擬試験の結果と偏差値によっては、志望校を再度絞り込む必要があるかもしれません。
ご本人の意思はもちろん、親御さんや学校・塾の先生などと相談する機会を設けておくと安心ですね。
【中学3年生の冬休み~入試】
いよいよ受験本番を迎える時期です。
これまで取り組んできた問題集や志望校の過去問題をくり返し解きましょう。
むやみやたらに様々な問題集に取り組むのではなく、解いたことのある問題を「くり返し解く」ことで知識が定着しやすく、また苦手な範囲を漏らさずに学習できます。
しかし、ここまで紹介したスケジュールは、ほんの一例にすぎません。
「中学1・2年生の内容で抜け漏れが多い」「難関高校を志望しており、すでに基礎は押さえている」など、習熟度や進み具合は人それぞれです。
勉強の進行度や苦手分野を見極めながら、無理の無い学習スケジュールを立てていきましょう。
高校生の受験勉強はいつから始めるべきか

高校生の受験勉強の流れも、中学生の高校受験と大まかな流れは共通しています。
しかし、大学受験特有の制度や傾向もありますので、特に意識しておきたい点をまとめました。
「英語」は文理問わず必須の科目
学部・学科を問わず出題され、どの大学受験においても必須科目となるのが「英語」です。
受験生全員が勉強することになりますが、英語は習熟するのに多くの時間を要し、基礎力が足りなければ大学受験の勉強に対応できません。
そのため、高校2年生までに基礎固めを終えている状況が理想的です。
英語学習においては、「リスニング」「リーディング」「ライティング」「スピーキング」の4技能を効率的に習得する必要があります。
リスニングは音読、リーティングには語彙や文法学習を重点的に行うなど、技能に合った勉強法を意識して取り組むのが効果的です。
苦手な技能がある場合は、勉強のやり方を相談してみるのも良いでしょう。
大学受験の英語は配点が高い傾向もあるので、志望校の出題形式・傾向を把握して、早めに対策を始めることをオススメします。
難関大学・国公立大学の受験勉強はいつから取り組むべき?
難関大学・国公立大学を志望する方は、高校1・2年生の段階から受験勉強をスタートするのが理想的です。
難関・国公立レベルの大学では入試問題の難易度が高いほか、記述問題や長文問題など大学独自の問題が出題される傾向にあるため、その対策に多くの時間を要します。
そのため、早い段階で基礎力を養い、応用レベルの演習や過去問対策に取り掛かる必要があるのです。
また、国公立大学の一次試験にあたる共通テストでは、6教科8科目程度の受験が一般的とされています。
広い出題範囲を巧みにカバーしていくには、早い段階からの受験勉強が求められるでしょう。
学校推薦型選抜・総合型選抜を狙うなら小論文・面接対策もしっかりと
たとえば、高校1・2年生から成果を出せており高い平均評定をキープできている方は、一般選抜だけでなく学校推薦型選抜や総合型選抜(旧:AO入試)のチャンスも得られるでしょう。
学校推薦型選抜や総合型選抜で受験する場合、小論文や面接が課せられるパターンが多いです。
そのため、面接形式(個人・集団)や質問事項、小論文の出題傾向は事前に調べられるので、高校3年生から準備しておくと良いでしょう。
また、成績だけでなく人柄も評価対象となりますので、普段から清潔感ある身だしなみや丁寧な言葉遣いを意識しておくと、本番も安心して臨むことができます。
高校受験・大学受験のどちらでも重要な共通点

中学生・高校生共に、受験するうえで押さえておきたい共通のポイントを3点まとめました。
「国語」「数学」「英語」は積み重ねが肝心
主要3科目とされる国語・数学・英語は、短期間で成績を伸ばすのが難しいと言われるほど、習得に時間がかかる教科です。
1年生の最初の範囲から受験前の学習範囲まで、油断することなく苦手分野を克服する習慣をつけましょう。
特に、大学受験では文系・理系を問わず「英語」は最重要科目となっていますので、高校受験の段階から英語を第一に学習を継続することで、将来の進路選択の幅を広げやすくなるかもしれません。
推薦希望者は1年次から高成績キープが必須
高校受験の内申点は公立の一般入試、公立・私立の推薦でも大事な評価基準となるので、多くの中学生にとっても合格に不可欠な数字と言えます。
また、大学受験で学校推薦を目指す場合も、最高学年になってから評定平均値を大幅に上げることは難しいとされているため、高1の段階からコツコツと成績アップを図り長期的な受験対策を継続する能力が求められます。
推薦入学を希望する方は、生活態度なども含めて「入学直後から」気を抜かずに学校生活を送るつもりで臨むと良いでしょう。
受験勉強のスタートは早ければ早いほど理想的
高校受験も大学受験も、入学時のスタートダッシュをどう決めたかで、今後の受験ライフの過ごしやすさが変わると言っても過言ではないでしょう。
早い段階から基礎力アップ&苦手克服に取り組むことで、時間的・精神的にゆとりが持てるようになり、今後の総復習や実践的な過去問題の対策に多くの時間を割くことができます。
受験勉強をいつから始めようか悩んでいる方は、自身の学年や学力、希望の入試形態を確認したうえで、入試日から逆算した学習プランを立てましょう。
実のある高校受験を叶えるなら、学研オンエアにお任せください!|まとめ
「高校受験の対策、いつから始めるべき?」「いつから、具体的に何から進めていくべきだろう?」とお悩みの方は、学研オンエアにご相談ください。
部活やイベントに忙しい中学生のお子さんの受験対策も、一流講師陣によるオンライン授業でしっかりサポートしていきます。
5教科使い放題の学習コンテンツや習熟度で選べるレベル別授業など、幅広く充実したスタディをお届けいたします。