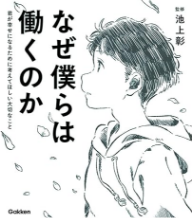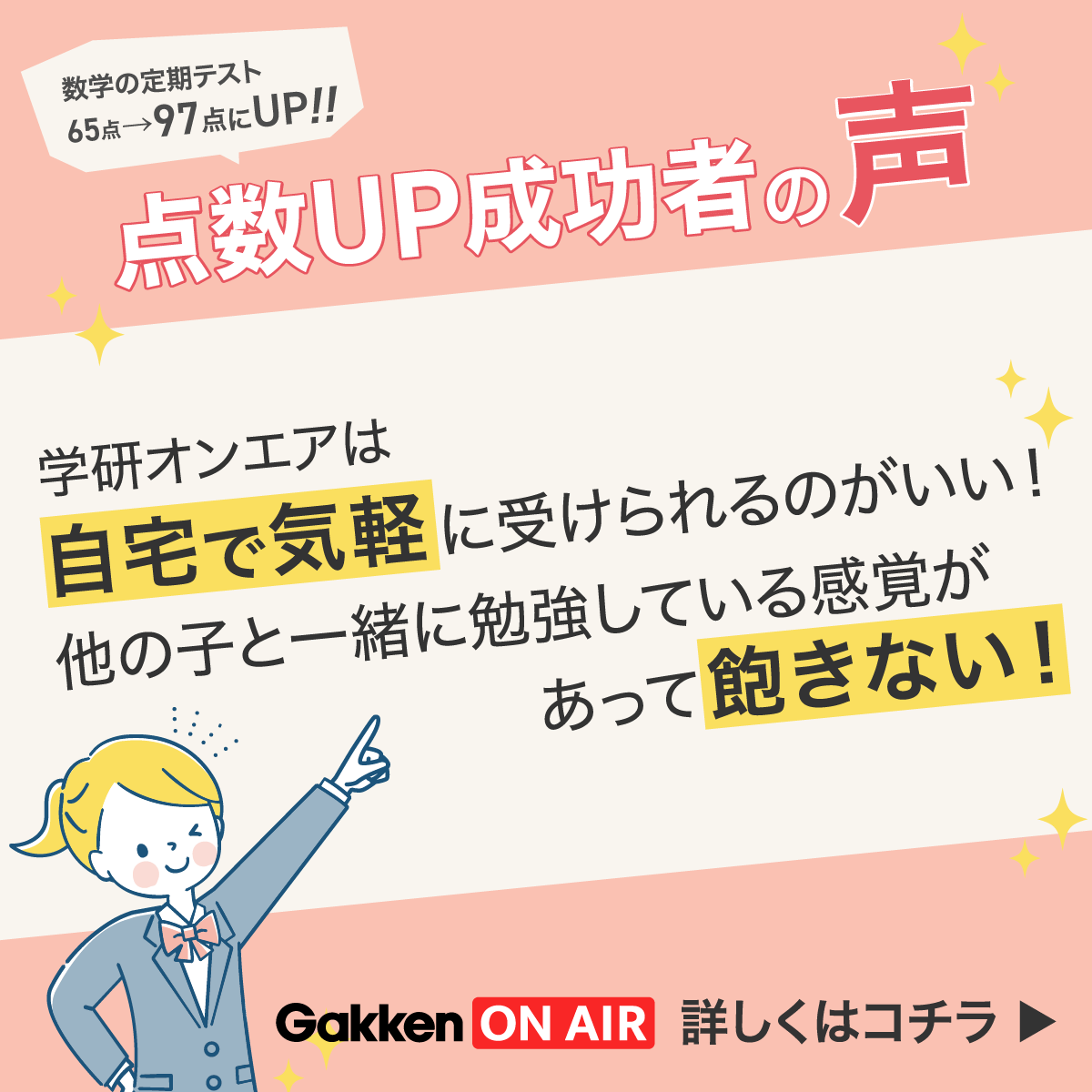「中学受験に向いてる子」と言うと、勉強が好きなお子さんや学力が高いお子さんをイメージしますよね。
しかし、上記以外でも、『中学受験の適性がある』と考えられるお子さんの特徴があります。
今回の記事では、中学受験に向く子・不向きな子の特徴や、中学受験のメリット、ご家庭で取り組めるサポート法について詳しく解説していきます。
中学受験に向いてる子の特徴7選

中学受験に向いていると考えられるお子さんの、代表的な特徴を7選ピックアップしました。
以下に記述する内面的な素養に優れているお子さんは、中学受験に向いてると言えるでしょう。
向いてる子の特徴①|知的好奇心・知識欲が旺盛
「どうして?」「なぜ?」と疑問を持ち、自ら知ろうとするお子さんは、知的好奇心が旺盛なお子さんと言えます。
中学受験を選択する場合、志望校合格のために多くの時間を勉強に費やすことになります。
そのため、学校の課題以外の問題集・調べ物にも意欲的に取り組めるようなお子さんだと望ましいでしょう。
素早く正確な情報処理能力が必要な算数・国語はもちろん、普段の勉強においては、しっかりと仕組みを理解するため、深く考えることも必要です。
特に、覚えることが多い理科・社会では日々の生活に関連する内容も多いため、興味を持って取り組めるかどうかで、お子さんの受験勉強の負担も変わっていくでしょう。
向いてる子の特徴②|年齢の割に大人びている
心理的な負担に耐えられる精神力や、欲求を抑制できるかどうかで、中学受験の適性を判断することができます。
合否が決まる受験では、幼いお子さんに少なからず心理的なストレスが生じるでしょうし、入試本番でベストなパフォーマンスを発揮することは、容易なことではありません。
また、合格には適切な学習習慣を身につける必要がありますが、年相応の「遊びたい」という欲求を抑えつつ、勉学に励まなければなりません。
よって、受験のプレッシャーや誘惑に打ち勝てるような、精神年齢が高いお子さんほど、中学受験に向いてると言えるでしょう。
向いてる子の特徴③|体が丈夫で健康
丈夫な身体や体調管理も、中学受験を乗り越えるために大切な要素です。
中学受験では、基礎となる知識を大量にインプットしたうえで、より応用的な問題を正確に解く力を培わなくてはなりません。
知識を大量にインプットするには長時間机に向かう必要があり、それには健康なコンディションが欠かせません。
また、中学受験は長期間にわたって対策を継続しなければなりません。
中学受験希望の小学6年生でも、週に4-5回通塾し終了時刻が21時になるケースも少なくありません。
受験シーズンの体調管理の徹底はもちろん、普段から「学習進捗」と「体の健康」にしっかりと気を配るようにしましょう。
向いてる子の特徴④|言われた通りに素直に取り組める
相手の説明をしっかりと聞き、指示された通りに取り組める素直なお子さんは、中学受験の適性が強い傾向にあります。
例えば、算数の新しい解法や考え方を学んだ際、すぐには理解できなかった経験はありませんか?
そういった時に、理解は追い付いてなくても、一旦、習った通りに何問か解き進めることができるお子さんは、着実に理解を深めていけるでしょう。
このような柔軟なチャレンジ精神が備わっているお子さんであれば、中学受験の勉強も無理なく継続しやすいと言えるでしょう。
向いてる子の特徴⑤|自己管理能力が高い
中学受験には、親御さんや塾のアシストはもちろん、お子さんご本人の自己管理能力も必須事項です。
自発的に勉強を始められる子どもは、目標を見据えて計画的に取り組みますが、スケジュール通りの学習をこなすには、自己管理能力が必要になります。
お子さんが慣れるまでご家庭で丁寧にサポートすることで、無理なく習慣化できるようになるでしょう。
例えば、「1日にゲームできる時間を決める」、「その日の学習プランを達成できたらお菓子をプレゼントする」などのルールを設けて、お子さんの学習態度に合わせて声かけを徐々に減らしていくと良いでしょう。
向いてる子の特徴⑥|競争心が強い
中学受験では、ほんのわずかな点差で合否が決まる世界に身を置くことになります。
そのため、強い競争心をもつお子さんであれば、それが受験勉強のモチベーションになると言えるでしょう。
競争心の強いお子さんは、合格のためにライバルよりも好成績を残そうと意欲的に学習に取り組みますし、競争を楽しみながら成績アップを目指すことができるでしょう。
全国のライバルを追い越すくらいの競争心があるお子さんであれば、精神的に弱ってしまう不安も少なく、中学受験に向いてると判断できます。
向いてる子の特徴⑦|やりたいこと・目標が明確
「あの学校の文化祭を盛り上げたい」「中学・高校の6年間は部活動に専念したい」など、やりたいことや目標があるお子さんは、中学受験に向いてると判断できます。
自ら目標設定を行うことで、自然と「頑張ろう」という気持ちが芽生えた経験はありませんか?
お子さんも同様で、目標をもって中学受験を希望するお子さんは目標達成に向けて勉強に取り組み、途中で落ち込みそうになっても、志望動機がお子さんを支えてくれるでしょう。
しかし、「友だちが同じ学校を受験するから」「親から受験を勧められたから」 など、受け身な動機の場合は、受験のモチベーションが低下してしまう可能性があります。
特に、保護者の方の意思で中学受験を検討しているご家庭は、「この学校で何をしてみたいか」「どんな中学生になりたいか」などをお子さまと話し合う時間を設けましょう。
お子さんの希望にマッチしそうな学校をピックアップし、実際に見学してみることで、お子さんの中学受験の意欲が湧いてくるかもしれません。
中学受験のメリット4選

中学受験を経験することで得られる、代表的なメリットを4つまとめました。
受験をする以上は絶対に合格したいところですが、①に関しては不合格だった場合でも有効なメリットです。
メリット①|中学受験勉強ならではの知識が身につく
中学受験の試験では、小学校の勉強だけでは太刀打ちできない「想像力・イメージ力を重視した難易度の高い問題」が出題されます。
算数の立体図形の問題であれば、紙面に書かれた立体をイメージする力が求められますし、国語では、物語の描写を適切に想像する能力を要します。
小学校の授業や宿題をこなすだけでは中学受験に合格できないので、中学受験向けの勉強に取り組むことで、中学受験ならではの知識を習得することができます。
たとえ受験に合格できなかったとしても習得した知識は残るので、お子さんの今後の学校生活や将来にも役立つでしょう。
メリット②|今後の受験で有利に働く
中学受験が必要な学校は、中高一貫校や大学附属校であることも多く、内部進学枠や内部推薦など優先的な制度が充実しており、高校受験が不要な傾向があります。
中高一貫校であれば、6年間という長い時間を大学受験の準備にあてることができるので、その後の受験でアドバンテージを得られるでしょう。
また、高校受験が無い分、部活動や習い事など、お子さんがやりたいことに集中しやすい点もメリットと言えます。
メリット③|教育&課外活動が充実
中学受験を行っている学校は、高水準な教育方針を掲げていたり、学業のほか課外活動にも力を入れている傾向にあります。
教育重視の学校は、様々な探究学習や体験学習などをカリキュラムに組み込むことで、生徒の視野を広げ、それぞれの才能や個性を高めていきます。
生徒が強く興味を持っている科目・活動に特化したプログラムや設備が充実している学校も多く、お子さんのペースで学びに集中できる環境が整っています。
学術的な知識を効果的に習得できたり、スポーツやアートなどの体験活動を通じてチームワークや感性を育むなど、様々なチャンスを期待できるでしょう。
メリット④|良質な人間関係に恵まれやすい
中学受験を経たお子さんやご家庭は、将来の大学進学まで見据えている方が多い傾向にあります。
そのため、入学後も意欲的に学習を継続する生徒が多く、お子さんの今後のモチベーションもキープしやすい環境と言えるでしょう。
また、中学生という多感な時期に、質の高い学友や先生と交流をもつことは、お子さんの人間性の成長に良い影響をもたらします。
学校生活で得られた人間関係は、お子さんの長い人生において素晴らしい財産になることでしょう。
中学受験に向いてる子をサポートするには?

【中学受験 = 親子の受験】と呼ばれるほど、保護者のサポートが中学受験に与える影響は大きいです。
ご家庭で取り組めるサポート法について具体的に解説いたしますので、中学受験を検討されている方は参考にしてみてください。
自ら勉強に取り組める環境をつくる
中学受験するにあたって、お子さんが自発的に勉強できる「環境づくり」が肝心です。
環境づくりをしていく上で重要なのは、【物理的環境】と【心理的環境】の2視点から変えていくことです。
【物理的な環境を変える】
お子さんが勉強するスペースや道具が整っていると、自然と「勉強に集中しよう」という意欲を高めることができます。
例1|子供部屋ではなく、リビングで勉強する。
例2|筆記具や教材など、机上には置くものは必要最低限に。
例3|誘惑の多いスマホやゲーム機には、必ず使用ルールを設ける。
例に挙げたような工夫をすることで、勉強に集中しやすい空間に変わっていくでしょう。
【心理的な環境を変える】
心理的な環境を変えるには、ご家族によるサポートが効果的と言えるでしょう。
お子さんに合わせて勉強に取り組みやすい習慣づくりをしたり、お子さんの努力やその過程、成果をしっかり褒めるのを忘れないようにしましょう。
例1|朝・夕方・帰宅後のように、勉強するタイミングを決めて習慣化する。
例2|付箋やホワイトボードなどのツールを活かして「To Do List 」を作成し、その日のうちにやるべきことを可視化する。
例3|「今日の小テスト満点とれたね!」など、小さなことにもお子さんの努力を見出して褒める。
例に挙げたようなご家庭による心理的なアシストは、お子さんのチャレンジ精神の向上につながるでしょう。
環境づくりのルーティン化は、ご家庭でお子さんに歩み寄る最大のサポートです。
「知的好奇心を刺激する」機会を増やす
知的好奇心が薄いお子さんを見て、心配な保護者の方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家庭でのちょっとしたやり取りから、引き出せるかもしれません。
お子さんが関心を持ちそうな時事ニュースの話題をふってみたり、お子さんが疑問をもった時に「一緒に理由を調べよう」と声かけをするなど、知的好奇心の芽は、ささいな日々の会話や体験の中に隠れているものです。
教科書や本で学ぶより、体験型の方が印象に残りやすいというお子さんも少なくありません。
科学館や博物館のような知的探求心を刺激するような施設にお出かけしたり、旅行を通じてその土地の文化や歴史に触れてみるのも良い機会になるでしょう。
あまり質問しないタイプのお子さんの場合は、こちらから「なぜ?」と考えさせるような質問を出してみる方法もオススメです。
このように「考える習慣」を積み重ねることで、だんだんと「知ることが楽しい!」「考えるって面白い!」という気持ちが育っていきます。
子どもの様子に合わせた声かけ・アドバイスを送る
中学受験は長期間にわたりますので、思うように結果が出ず、気持ちが沈んでしまう時もあるでしょう。
そんなときこそ、お子さんはご家族からエールを欲します。
しかし、ただエールを送るだけでなく、『過程』に着目して褒めることをオススメします。
例えば「先週より多くの漢字を読めるようになったよね」「毎日サボらずに朝学習できてスゴイ!」というようなエールを心がけることで、お子さんがつらい時期でもモチベーションを維持することができるでしょう。
このような前向きなエールは、お子さんの意欲と自己肯定感を着実に培ってくれます。
中学受験に向いていない子をサポートするには?

「ウチの子は中学受験に向いてないかもしれないけど、挑戦してみたい!」と考えるご家庭もいらっしゃるでしょう。
以下に向いていないと思われるお子さんの特徴を記載しました。
もし当てはまったとしても、その次に「向き・不向き問わず中学受験で必要な心構え」について解説しているので、そちらもふまえてご覧いただくことをオススメします。
中学受験に向いていないと感じる子の特徴
【自発的な勉強が苦手なお子さん・勉強に苦手意識のあるお子さん・集中力に欠けるお子さん】
中学受験を乗り越えるには、「積極的に勉強に取り組む姿勢」も大切な要素の一つ。
指摘されるまで宿題をやらなかったり、やる気の落差が激しいなどの特徴があるお子さんは、中学受験の勉強に耐えられないかもしれません。
【受験する目標が曖昧なお子さん】
志望校への具体的な動機が無かったり、進学後の理想像をイメージできていない状態で、お子さんの学習意欲をキープしづらい傾向にあります。
受け身の状態で学習を続けていくうちに、「本当にその学校を受験したいのかな?」という迷いが生じ、苦痛に感じる時間が長くなってしまうかもしれません。
向き不向きではなく、お子さんのタイプや適性に合わせたフォローが大切

中学受験に向いてる子の特徴や受験アドバイス、向いていない子の特徴についてご紹介してきました。
しかし、「向いてる子の特徴に多く当てはまっているし、うちの子は受験で成功できるはず」、「向いてる子じゃないから、中学受験を諦めるべき」 と一概に言い切れません。
受験合格の要は学力であり、それは日々の学習習慣を積み重ねることによって養われていきます。
そのため、「受験勉強のやり方が合っているか」を、お子さんの様子に合わせて調整していく必要があります。
ある程度の自己管理能力・集中力を要する中学受験ですが、それらに欠けるからといって中学受験ができない訳ではなく、環境やご家庭のサポート次第で、お子さんの学力や人間性を高めることができます。
お子さんの向き・不向きを問わず、有意義な中学受験には周囲のサポートが不可欠|まとめ
中学受験に関するご相談なら、幅広く充実したオンライン塾 Gakken ON AIRにお任せください。
通塾の負担を軽減し、オンラインライブ授業・デジタル教材もお子さんのペースでご利用いただけるので、自発的な学習を促すことができるでしょう。
中学受験の有無を問わず、お子さんの有意義な学力向上&習慣化を全力でサポートいたします。