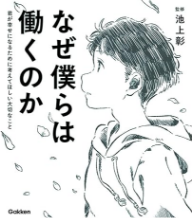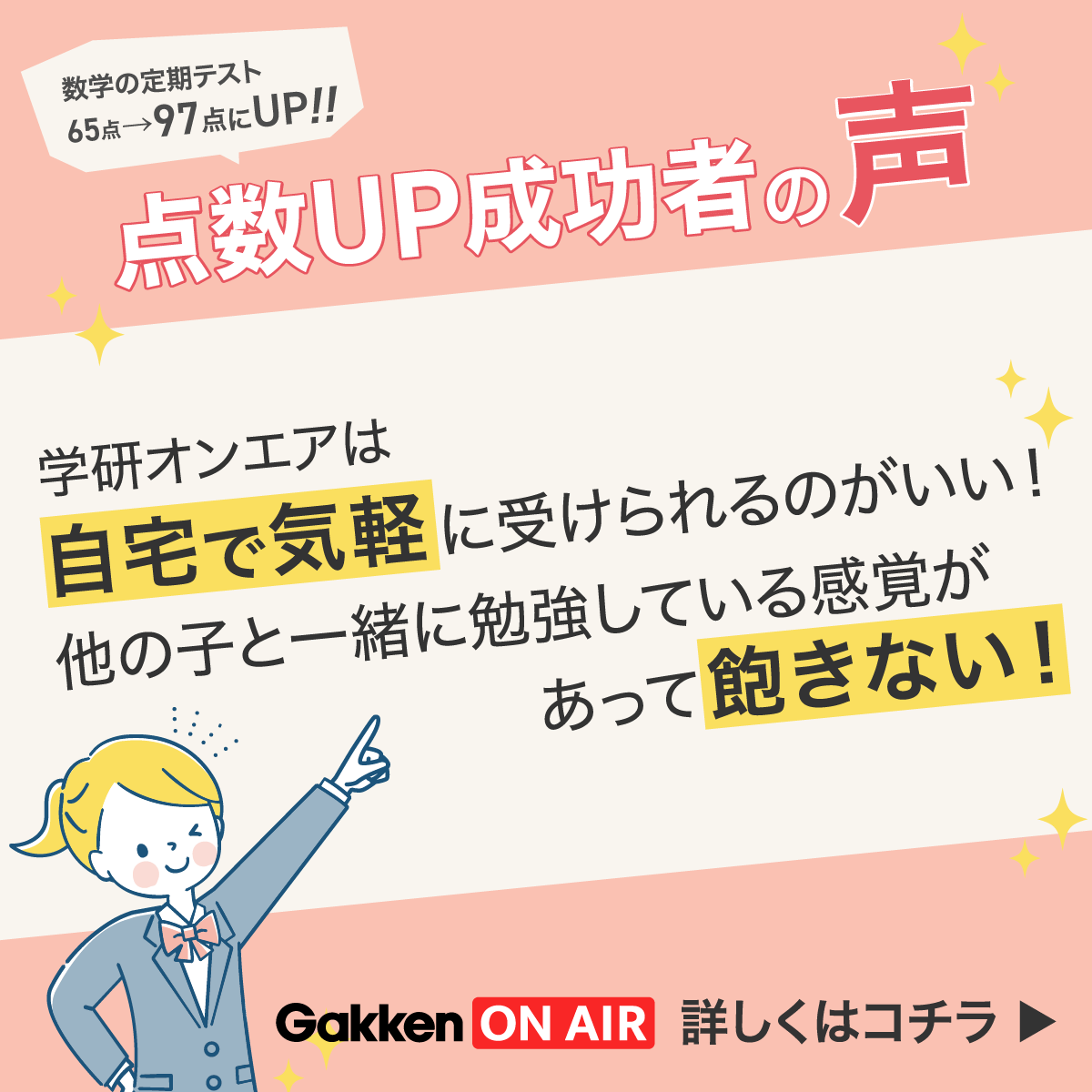中学や高校受験の志望校を決める際に、倍率が気になった経験はありますか。
倍率は志望校の人気や難易度を示す指標の1つです。
ただし、受験の難易度と必ずしもイコールではありません。
本記事では受験の倍率や難易度との違い、および倍率より大事なポイントについて解説します。
これから受験を考えている生徒や親御さんは参考にしてください。
倍率とは?

入学試験の前に、志望校選びの参考になる指標の1つが倍率です。
倍率は志望校を受験した際に「〇人に1人が合格する」の「〇」の部分にあたります。
たとえば倍率が3倍なら、3人に1人が合格する計算です。
単純に考えると倍率が高ければ高いほど合格が難しいと思いがちです。
しかし、倍率と受験の難易度は必ずしも比例しません。
受験に関する3つの倍率について

受験に関する倍率は大きく以下の3つに分類されます。
- 志望倍率
- 受験倍率
- 実倍率
それぞれについて解説します。
受験に関する3つの倍率①志望倍率
受験に関する倍率の1つが志望倍率です。
志望倍率は出願倍率や応募倍率とも呼ばれており、受験を前に確認するのが基本です。
志望倍率は「志望者(出願者)÷募集定員」で割り出せます。
たとえば募集定員が50名の学校(学部)に対して100名の志願(応募)があった場合、倍率は「100÷50」=2倍です。
ただし、都道府県によりますが、公立高校の多くが一度だけ志願先の変更を認めています。
そのため、志望倍率が高いからと志願先を変更しても、同じように考える方が多いとかえって変更した先の志望倍率を高めてしまう可能性があります。
受験に関する3つの倍率②受験倍率
受験倍率は実際に受験した人の数から算出される倍率です。
一度は志望先に出願したものの、何らかの事情があり(病気や入試の取りやめなど)、実際には受験しないケースがあります。
実質倍率は「実際に受験した人の数÷募集定員」で割り出せます。
たとえば募集定員60名の学校(学部)を受験した生徒の数が150名の場合「150÷60」=2.5が受験倍率です。
受験に関する3つの倍率③実倍率
実倍率(実質倍率)は、実際に入学試験に合格した割合を示します。
実倍率は公立校ではなく、私立高の合格率に関わる点が特徴です。
公立校では一般に応募人数を大きく上回る合格者を出すことはありません。
一方、私立高の場合は掛け持ちで受験する生徒が多く合格しても入学しないケースがあるため、募集定員より多くの合格者を出す傾向にあります。
仮に募集定員が50名であっても合格者が75名の場合、実質倍率は「50÷75」=0.67です。
倍率が変動する要因について

中学や高校を受験する際の指標となる倍率ですが、以下の要因で変動するケースが少なくありません。
- 記念受験
- 受験日
- 志願先変更
- 併願
それぞれについて解説します。
倍率が変動する要因①記念受験
倍率が変動する要因の1つが記念受験です。
記念受験とは合格する気がない、もしくは合格の見込みが低いと分かっているのに、記念や経験のために受験することを意味します。
また、まぐれでの合格を期待して記念受験するケースも少なくありません。
とくに「男子御三家」「女子御三家」を記念受験する生徒は多く、志望倍率が高くなる傾向にあります。
倍率が変動する要因②受験日
受験日が要因となり倍率に変動をもたらすケースがあります。
たとえば私立中学の一部では、日曜日に受験を実施するケースがあります。
一般的な中学校は平日が受験日のため、日曜日に受験できると併願の状況が変化し倍率が高くなる訳です。
日曜日に受験できる学校の倍率が上がる現象を、サンデーショックと呼ぶことがあります。
キリスト教系の私立中学は日曜日に入試を実施するケースも多いため、事前にチェックしておく必要があります。
倍率が変動する要因③志願先変更
公立高校の倍率が変動する要因として、志願先の変更が挙げられます。
都道府県にもよりますが、公立高校では最初の倍率が発表されてから一度だけ志願先を変更できるケースが少なくありません。
最初の倍率を見てそのまま受験しても、志望校を再度見直しても構いません。
ただし、変更した先の学校の倍率が高くなるケースも多いため、変更の際は学校や塾の先生に相談するのがおすすめです。
倍率が変動する要因④併願
併願制度も倍率が変動する一因です。
多くの私立高校では併願を見越して募集定員よりも多くの合格者を出す傾向があります。
そのため、受験倍率と実倍率との間に大きな差が出がちです。
倍率が1未満ってどういうこと?

志望校の倍率が1未満の状態を定員割れと呼んでいます。
定員割れは志望者の数が募集定員を下回っている状態のため、受験者がすべて合格できるイメージを持たれがちです。
しかし、実際には受験者全員が入学できるとは限りません。
中学校とは異なり高校は義務教育ではないため、受験生のカラーが校風に合っていないと判断されれば、定員割れを超している学校でも落とされるケースがあります。
倍率よりも大事なポイント

ここまで入学試験における倍率について詳しく解説しましたが、大事なポイントは倍率と合格率には必ずしも有意な関係性がない点です。
私立中学や高校では受験に際して、最低ラインを設定しているケースがほとんどです。
そのため、少なくとも最低ラインを超える学力を備えておく必要があります。
また、倍率は記念受験や私立校の併願によっても左右されるため、倍率が高いからといって必ずしも合格率が低くなるわけではありません。
倍率よりも定期テストや模擬試験の結果および偏差値を把握し、自分の学力に合った中学校・高校を選ぶのが大切なポイントです。
倍率に関してよくある質問

入試における倍率に関して、以下3つの質問が多く寄せられています。
- 倍率1未満なら受験生全てが入学できる?
- 倍率が低い高校の方が合格しやすい?
- 倍率が高い高校は偏差値も高い?
それぞれの質問にお答えします。
倍率に関する質問①倍率1未満なら受験生全てが入学できる?
倍率に関して多く寄せられる質問の1つが、倍率1未満なら受験生全てが入学できるかとの問いです。
結論から申し上げますと、倍率が1未満でもすべての受験生が合格できるわけではありません。
公立高校を受験する場合であっても、多くの学校で面接を実施しています。
面接では入学を希望する理由だけでなく、学習意欲や将来の展望を聞かれたり、面接中の態度を見られたりします。
倍率1未満でも生徒が校風にそぐわないと判断されれば、面接で落とされるケースが少なくありません。
倍率に関する質問②倍率が低い高校の方が合格しやすい?
倍率が低い高校の方が合格しやすいと考えられがちです。
しかし、倍率が低いから合格しやすいとは限りません。
倍率が低い理由はさまざまですが、偏差値が高くて応募者が少ないケースもあるためです。
志望校を決める際には過去の応募者だけでなく、偏差値も確認しておくことが欠かせません。
倍率に関する質問③倍率が高い高校は偏差値も高い?
倍率の高さと偏差値は相関関係にありません。
偏差値が低くて倍率が高い学校もあれば、その逆のケースもあります。
偏差値は自分の現在の学力を客観的に判断するための指標です。
志望校を決める際には、倍率ではなく偏差値をより重視すべきでしょう。
倍率とは?|まとめ
受験の際は倍率を参考にするのが基本です。
受験前に発表されるのは志願倍率ですが、倍率と合格率は必ずしも比例しません。
学校を選ぶ際には生徒の偏差値を基に、実際に学校を見学して志望校を絞るのがおすすめです。
今回の記事を参考に倍率について正しく理解し、志望校選びの参考にしてください。